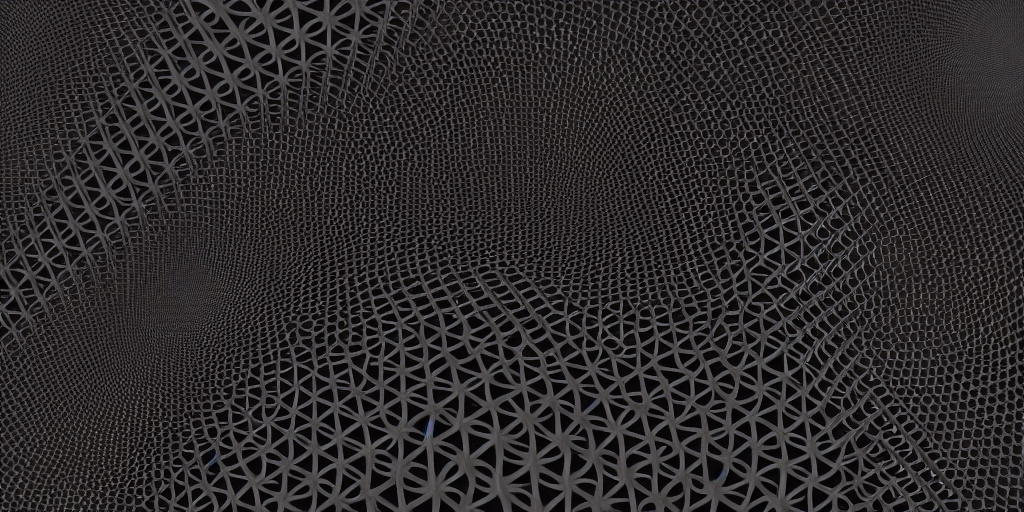ポケットペアのニュースリリース
2025年5月8日に、『パルワールド』の開発元である株式会社ポケットペアから以下のニュースリリースがありました。訴訟の進行に左右されることなく開発・配信を継続できるよう、予防的措置として「パルスフィアによる召喚」機能を削除し、「プレイヤーのそばで直接召喚する」仕様に変更したほか、滑空機能についても今後はアイテムを使用する形へと変更したとのことです。
係属中の訴訟に関するパルワールドの仕様変更と今後について
https://www.pocketpair.jp/news/20250508?lang=ja
変更後の仕様が特許権の非侵害であると認められれば、ゲームの差止めと仕様変更以後の損害賠償を免れることができるため、訴訟対応として一般的に行われる方法です。これらの仕様変更がなぜ特許権侵害を回避できるのか、以下に技術的な解説を行います。
パッチv0.3.11「プレイヤーのそばに直接パルを召喚する」仕様変更
2024年11月30日に公開したパッチv0.3.11では、「パルスフィアを投げてパルを召喚する」機能を削除し、代わりに「プレイヤーのそばに直接召喚する」仕様へと変更しました。パルワールドでは、フィールド上にいるパル(捕獲対象キャラクタ)にパルスフィアという捕獲アイテムを投げ当てて捕獲します。捕獲したパルはプレイヤーキャラクタの仲間キャラクタとして戦闘やクラフト(建築、道具作り、料理、栽培等)を手伝わせることができます。捕獲したパルはパルスフィアに格納して必要に応じて出し入れできるのですが、仕様変更前は捕獲したパルを格納したパルスフィアを構えて投げることでパルスフィアからパルを呼び出す仕様でした。仕様変更後は「構える→照準を決める→投げる」という動作がなくなり、1つのボタン操作を行うとプレイヤキャラクタの近くにボンとパルが出現する仕様になりました。
つまり、本仕様変更により以下の動作がなくなりました。
・戦闘キャラクタを放つために構える動作
・戦闘キャラクタを前記照準方向に向けて放つ動作
特許請求の範囲に記載された構成を全て充足する場合に特許権侵害と判断されます。パッチv0.3.11の仕様変更により、特許7545191の請求項1(請求項7、19にも同様の表現あり)の以下に下線で示した構成(1B、1C、1D、1E)を充足しなくなりました。
特許7545191の請求項1
| 1A | コンピュータに、 | |
| 1B | 操作ボタンを押下する操作入力に基づいて、仮想空間内のフィールド上に配置されたフィールドキャラクタを捕獲するための捕獲アイテムが複数種類含まれる第1のカテゴリ群が選択されている場合に、前記捕獲アイテムを放つために構える動作を、戦闘を行う戦闘キャラクタが複数種類含まれる第2のカテゴリ群が選択されている場合に、前記戦闘キャラクタを放つために構える動作を、前記仮想空間内のプレイヤキャラクタに行わせ、 | プレイヤキャラクタにパルを格納したパルスフィアを構えさせる操作 |
| 1C | 方向入力に基づいて、前記仮想空間内における照準方向を決定させ、 | 照準方向を決める操作 |
| 1D | 前記操作ボタンとは異なる操作ボタンによる操作入力に基づいて、前記第1のカテゴリ群が選択されている場合に当該第1のカテゴリ群に含まれる前記捕獲アイテムを、前記第2のカテゴリ群が選択されている場合に当該第2のカテゴリ群に含まれる前記戦闘キャラクタをさらに選択させ、 | パルスフィアを構えている間に、構えていたパルとは異なるパルを選択する操作 |
| 1E | 前記構える動作を前記プレイヤキャラクタに行わせる際に押下している前記操作ボタンを離す操作入力に基づいて、前記捕獲アイテムが選択されている場合に、選択された前記捕獲アイテムを前記照準方向に向けて放つ動作を、前記戦闘キャラクタが選択されている場合に、選択された前記戦闘キャラクタを前記照準方向に向けて放つ動作を、前記プレイヤキャラクタに行わせ、 | 構えたパルスフィアを照準方向に向けて放つ動作を行わせる操作 |
| 1F | 前記捕獲アイテムが放たれて前記フィールドキャラクタに命中した場合、前記捕獲が成功するか否かに関する捕獲成功判定を行わせ、 | |
| 1G | 前記捕獲成功判定が肯定判定された場合に、前記捕獲アイテムが命中した前記フィールドキャラクタをプレイヤが所有する状態に設定させ、 | |
| 1H | 前記戦闘キャラクタが前記フィールドキャラクタと戦闘可能な場所に放たれた場合に、当該戦闘キャラクタと当該フィールドキャラクタとの前記フィールド上における戦闘を開始させる、ゲームプログラム。 |
特許7493117の請求項1
特許7493117の請求項1は捕獲アイテムを投げる操作に関する内容のみです。
| 1A | 情報処理装置のコンピュータに、 |
| 1B | 第1のモードにおいて、 |
| 1C | 方向入力である第1の操作入力に基づいて、仮想空間内における照準方向を決定させ、 |
| 1D | 第2の操作入力が行われた場合に、前記照準方向を仮想空間内のフィールド上に配置されたフィールドキャラクタに向けさせるとともに、第1の指標を表示させ、 |
| 1E | 第3の操作入力に基づいて、前記照準方向に前記フィールドキャラクタを捕獲するための捕獲アイテムを放つ動作をプレイヤキャラクタに行わせ、 |
| 1F | 前記捕獲アイテムが前記フィールドキャラクタに命中した場合、捕獲が成功するか否かに関する捕獲成功判定を行わせ、 |
| 1G | 前記第1の指標は、前記捕獲成功判定の肯定判定し易さを示す情報である、ゲームプログラム。 |
特許7493117の請求項2
請求項2は、請求項1を引用するもので、「戦闘キャラクタを放つ動作」に関する内容です。
この請求項における「戦闘キャラクタを放つ動作」とは、2Bの記載を読む限り、構える、照準を定める、投げるといった一連の具体的動作を意味しているわけではありません。したがって、パルワールドの仕様変更後も「戦闘キャラクタを放つ」という操作そのものは依然として存在しています。しかし、仕様変更後のパルワールドでは、「戦闘キャラクタを放つ動作をプレイヤキャラクタに行わせる」仕様ではなくなっています。また、請求項1の1Bに記載された「第1のモード」や、請求項2の2Bに記載された「第2のモード」のようなモード切替自体がパルワールドには存在していません。この点については過去の記事でも指摘してきましたが、パッチv0.3.11による仕様変更により、少なくとも請求項2の2Bが要求する構成要件は満たされなくなったと考えられます。
| 2A | 前記捕獲に成功した前記フィールドキャラクタは、戦闘を行う戦闘キャラクタとしてユーザが利用可能であって、 | |
| 2B | 前記コンピュータに、さらに、第2のモードにおいて、前記プレイヤが所有する前記戦闘キャラクタを放つ動作を前記プレイヤキャラクタに行わせ、当該戦闘キャラクタと前記フィールドキャラクタとの前記フィールド上における戦闘を行わせる、請求項1記載のゲームプログラム。 | プレイヤキャラクタにパルを格納したパルスフィアを放つ動作を行わせる操作 |
パッチv0.5.5「グライダーパル」による滑空の仕様変更
パッチv0.5.5では、グライダーパルによる滑空の仕様が変更されました。従来は、グライダーパルを直接呼び出してプレイヤーキャラクタが掴まるなどして滑空していましたが、今後は「グライダー」というアイテムを装備することで滑空を行い、その性能にグライダーパルの能力が追加効果として反映される方式に改められました。
仕様変更前のように、プレイヤーキャラクタがグライダーパルに掴まって滑空する形態は、特許第7528390号の請求項1の1D「前記プレイヤキャラクタが前記空中用搭乗キャラクタに搭乗中に、操作入力に基づいて前記空中用搭乗キャラクタに搭乗した前記プレイヤキャラクタを空中において移動させる」に該当する可能性がありました。あるいは訴訟における任天堂側の準備書面でそのような指摘があったのかも知れません。
なお、「搭乗」という語は辞書的には「飛行機・艦船などに乗り込むこと」を指しますが、本特許の明細書(段落0082)では、「プレイヤキャラクタが搭乗キャラクタに掴まること、ぶら下がることを含む」と定義されています。
今回の仕様変更によって、滑空は「グライダー」アイテムの効果として行われるようになったため、プレイヤーキャラクタが搭乗キャラクタに掴まる、ぶら下がる、あるいは一体的に移動可能な状態になるといった形態には該当しない仕様になったと考えられます。
特許7528390の請求項1
| 1A | 情報処理装置のコンピュータに、 |
| 1B | 仮想空間内において、操作入力に基づいてプレイヤキャラクタを制御させ、 |
| 1C | 前記プレイヤキャラクタが所有する所有キャラクタのうち、前記プレイヤキャラクタが搭乗可能な複数種類の搭乗キャラクタのいずれかが選択されて搭乗指示が行われた場合、前記プレイヤキャラクタを当該選択された前記搭乗キャラクタに搭乗させて、移動可能な状態にさせ、 |
| 1D | 前記プレイヤキャラクタが空中にいるときに第1の操作入力が行われた場合、前記プレイヤキャラクタを前記搭乗キャラクタのうち、空中を移動可能な空中用搭乗キャラクタに搭乗させて、空中において移動可能な状態にさせ、 |
| 1E | 前記プレイヤキャラクタが前記空中用搭乗キャラクタに搭乗中に、操作入力に基づいて前記空中用搭乗キャラクタに搭乗した前記プレイヤキャラクタを空中において移動させる、ゲームプログラム。 |
特許7528390の明細書抜粋
【0082】
複数の所有キャラクタの中には、プレイヤキャラクタ70が搭乗(ライド)することができる所有キャラクタがある。プレイヤキャラクタ70が搭乗することができる所有キャラクタを、「搭乗キャラクタ」という。なお、ここで「プレイヤキャラクタ70が搭乗キャラクタに搭乗する」とは、プレイヤキャラクタ70が、搭乗キャラクタと一体となって移動可能な状態になることを意味する。例えば、「プレイヤキャラクタ70が搭乗キャラクタに搭乗すること」は、プレイヤキャラクタ70が搭乗キャラクタの上に乗ること、プレイヤキャラクタ70が搭乗キャラクタに掴まること、プレイヤキャラクタ70が搭乗キャラクタにぶら下がることを含む。なお、プレイヤキャラクタ70と搭乗キャラクタとが、直接的に接触する場合に限らず間接的に接触して一体的に移動可能な状態になる場合も、「プレイヤキャラクタ70が搭乗キャラクタに搭乗する」ことに含まれる。
なぜ「グライダー」の追加効果であれば大丈夫なのか
パッチv0.5.5の仕様変更により、基本的には上記の「搭乗」の用語の解釈で非侵害になると考えられます。つまり、プレイヤキャラクタが直接触れるのはアイテムであるグライダーであり、グライダーパルはグライダーの機能には影響を及ぼすものの、グライダーパル自体はグライダーに接触していないため「間接的に接触して一体的に移動可能な状態」にはなってないといえます。
本件については上記に加え、審査過程における特許庁と任天堂のやりとりからも、「グライダーは搭乗キャラクタではない」といえます。以下に、特許7528390の拒絶理由通知書(特許庁から任天堂への最初の審査結果の通知)と、意見書(拒絶理由通知書を受けた任天堂の特許庁への反論)の抜粋を載せます。
特許7528390の拒絶理由通知書(特許庁の審査)の抜粋
特許庁は、「ARK: Survival Evolved」というゲームにおいて、落下中にパラシュートを使用して移動キーを操作する空中で移動ができること等が記載されているため新規性、進歩性なしと指摘していました。
●理由2(新規性)及び理由3(進歩性)について
・請求項1,3,5,7,9,11,13,15
・引用文献等 1
・備考
(1)請求項1,3,5,7,9,11,13,15 引用文献1(特に”使用法”を参照)には、「ARK: Survival Evolved」というゲームにおいて、落下中(空中にいるとき) に、インベントリからパラシュートを使用し、移動キーを押すことで、飛行中にさまざまな方向に移動(操作入力に基づいて、空中用搭乗オブジェクトに搭乗したプレイヤキャラクタを空中において移動)できること、 パラシュートは、誤って飛行生物(搭乗オブジェクト)の騎乗を解除した場合に 、自分(プレイヤキャラクタ)を救うために使用でき、落下中の速度を低下させ、致命的な損傷を防ぐ可能性があることが記載されている。 ここで、インベントリからパラシュートを使用する際には、何らかの操作入力 が行われる蓋然性が高い。
また、引用文献1のパラシュートが、落下中の速度を低下させて致命的な損傷を防ぐ可能性があることを踏まえれば、「プレイヤキャラクタが所定の基準を超える高さから、又は、所定の基準を超える速度で空中から地面に落下した場合に、プレイヤキャラクタに所定のダメージを与えさせる」ことは、引用文献1に記載されているに等しい事項である。
よって、本願の請求項1,3,5,7,9,11,13,15に係る発明と引 用文献1に記載された発明との間に、発明特定事項の差異はない。また、本願の請求項1,3,5,7,9,11,13,15に係る発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に想到し得たものである。
特許7528390の意見書(任天堂の反論)の抜粋
上記の拒絶理由通知書に対し、任天堂は次のように反論しました。
「引用文献1に記載のパラシュートは、確かにプレイヤキャラクタが使用可能な『道具』であるが、『キャラクタ』ではなく、本願発明における『所有キャラクタ』や『搭乗キャラクタ』には該当しない。」つまり、パラシュートはあくまで道具であり、搭乗キャラクタには当たらないと主張したのです。そして、この反論が認められ、特許査定に至りました。
パラシュートとグライダーは厳密には異なる道具ですが、「空中で使用して落下速度を抑え、所望の方向へ移動できる」という用途は共通しています。
このような経緯がある以上、任天堂が訴訟において「グライダーは搭乗キャラクタである」と、過去の意見書とは逆の主張を行うことは許されません。
このように、出願時にした主張と矛盾する主張を後に行うことを禁じる法理を「包袋禁反言(ほうたいきんはんげん)」の原則といいます。
3.2 理由2、3について
(1)引用文献について
引用文献1には、「パラシュートは、落下中の速度を低下させ、致命的な損傷を防ぐ可能性があります。安全に崖から降りたり、着陸せずに敵の基地に飛び込んだり、あなたが誤って飛行生物の騎乗を解除した場合に自分を救ったりするために使用できます」との記載、「落下中、インベントリからパラシュートを使用し、後方への移動キー(デフォルト はS)を押して落下を遅くします。自動的にアクティブになるわけではないため、必要だ と思われる場合はホットバーに入れることをお勧めします」との記載があります。
(2)本願発明について
本願請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という)は、「仮想空間内において、操作入力に基づいてプレイヤキャラクタを制御させ、前記プレイヤキャラクタが所有する所有キャラクタのうち、前記プレイヤキャラクタが搭乗可能な複数種類の搭乗キャラクタのいずれかが選択されて搭乗指示が行われた場合、前記プレイヤキャラクタを当該選択された前記搭乗キャラクタに搭乗させて、移動可能な状態にさせ」ることを前提として、「前記プレイヤキャラクタが空中にいるときに第1の操作入力が行われた場合、前記プレイヤキャラクタを前記搭乗キャラクタのうち、空中を移動可能な空中用搭乗キャラクタに搭乗させて、空中において移動可能な状態にさせ」「前記プレイヤキャラクタが前記空中用搭乗キャラクタに搭乗中に、操作入力に基づいて前記空中用搭乗キャラクタに搭乗した前記 プレイヤキャラクタを空中において移動させる」ことを特徴としています。
(3)本願発明と引用文献1に記載の発明との対比
引用文献1のパラシュートは、そもそも、引用文献1の表に記載のように、プレイヤキャラクタが使用することができる「道具」であるものの、「キャラクタ」ではなく、本願発明の「所有キャラクタ」や「搭乗キャラクタ」ではありません。
引用文献1では、パラシュートは、(プレイヤーが)誤って飛行生物の騎乗を解除した場合に自分を救ったりするために使用できることが記載されていますが、この記載は、空中用搭乗キャラクタに搭乗させることができないために飛行生物とは無関係な道具であるパラシュートを別途使用せざるを得ないことを意味します。すなわち、引用文献1では、 空中で飛行生物の騎乗を解除した場合には、飛行生物に搭乗させることができません。したがって、引用文献1には、プレイヤキャラクタが空中にいるときにプレイヤキャラクタを空中用搭乗キャラクタに搭乗させることは記載されていません。
したがって、「前記プレイヤキャラクタが空中にいるときに第1の操作入力が行われた 場合、前記プレイヤキャラクタを前記搭乗キャラクタのうち、空中を移動可能な空中用搭乗キャラクタに搭乗させて、空中において移動可能な状態にさせ」ることは、引用文献1には記載も示唆もされていません(相違点1)。
また、引用文献1では、「飛行生物」が「プレイヤキャラクタが所有する所有キャラクタ」であることは記載されていません。すなわち、引用文献1の「飛行生物」は、本願の 「プレイヤキャラクタが所有する所有キャラクタ」の一種である「飛行用搭乗キャラクタ 」とは異なります。
したがって、引用文献1には「前記プレイヤキャラクタが所有する所有キャラクタのうち、前記プレイヤキャラクタが搭乗可能な複数種類の搭乗キャラクタのいずれかが選択されて搭乗指示が行われた場合、前記プレイヤキャラクタを当該選択された前記搭乗キャラクタに搭乗させて、移動可能な状態にさせ」ることは記載されていません(相違点2)。
差止請求と損害賠償請求に対する影響
差止請求に対する影響
差止請求とは、現在および将来における侵害行為の停止又は予防を請求することをいいます。仕様変更により、訴訟で問題とされている仕様が現在の製品には存在しない状態となります。したがって、仮に原告の特許が有効かつ侵害が認められたとしても、「現在の仕様に基づく販売・提供行為は侵害に該当しない」という主張が可能になります。このため、差止請求の必要性や正当性が低下し、裁判所が差止を認める可能性が低下します。また、被告が「今後も旧仕様に戻さない」と明言している点は、差止の必要性がないと判断される材料になります。
損害賠償請求に対する影響
損害賠償請求は、過去の侵害行為によって発生した損害について請求されるものです。旧仕様が特許権侵害であると判断された場合は、特許権の設定登録日から仕様変更日までの期間に関して損害賠償責任が問われる可能性があります。しかし、変更した仕様が特許権の非侵害であれば、仕様変更後の実施行為については特許権侵害とはならないため、損害額を限定的にすることができます。
特許権非侵害を確信しているのであれば仕様変更をする必要はないのか
ポケットペア社の5月8日のリリースに関して、「特許権非侵害を確信しているのであれば仕様変更をする必要はないのでは?」、「仕様変更をするのは自信がないからではないのか」といった意見がネット上で散見されました。一般論としては理解できますが、以下の理由から訴訟においてこの理屈は成り立ちません。
訴訟における「勝ち筋」と「リスク回避」は別の次元
- 特許無効や非侵害に自信があっても、訴訟の結果は必ずしも予測通りに進むとは限りません。裁判には審理の長期化、審判官の判断の揺れ、予期せぬ証拠提出などの不確実性が常につきまといます。
- そのため、「勝てるから変えない」ではなく、「万一に備えて変える」のは、リスク管理上当然の対応です。
差止リスクを防ぎ、プレイヤーへの影響を最小化する意図
- 万が一、旧仕様が侵害と判断された場合、配信停止等の差止命令が下されるリスクがあります。
- それによりユーザーがゲームをプレイできなくなれば、ブランド価値の毀損、顧客離れにつながります。
- そうした“最悪の事態”を予防しつつサービス提供を継続するには、仮に係争中であっても事前に仕様を変更することが極めて合理的です。
仕様変更は「自信のなさ」ではなく「戦略的自衛」
- 特許が無効になる可能性や非侵害が認められる可能性を見据えつつも、「現実の裁判制度とビジネスの継続を両立させるために仕様変更する」ことは、防御的かつ戦略的な対応です。
- 特に、ゲーム業界のようにアップデート可能な分野では、技術的代替手段が存在するなら、あえて危険な仕様に固執しないという判断も合理的です。